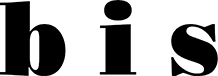Interview / 2020.02.05
【インタビュー】甘くて闇のあるブランド「Katie」デザイナー・三井リンダの作る世界観とは
可愛くてドリーミーで憧れる。そんな世界をつくり続けるクリエイターに今までのこと、これからのことをインタビュー。今回お話を伺ったのは、東京・代官山に「Katie(ケイティ)」を立ち上げた三井リンダさん。類まれなセンスや感覚を培った過去、現在、そして今後に迫ります♡
Interview
1997年に誕生した「Katie(ケイティ)」。’90年代にはまだ存在しなかったファッションとガーリーカルチャーをつなぎ、見たことのないライフスタイルを形にしました。今もなおbisの読者をはじめ、たくさんの女の子達を熱狂させています。手掛けるのは創業から変わらない二人の女性、LINDAさんとTAKIさん。’90年代に出会った二人は気持ちのおもむくままに、でも一方で驚くほど冷静な目を持つ抜群のバランス感覚で、ガーリーカルチャーを牽引してきました。当時20代だった二人はどのように商売を成り立たせ、22年にわたりブランドを続けてきたのか。LINDAさんにお話を伺いました。
「TAKIちゃんとは、当時私が働いていたヒステリックグラマーで出会ったんです。共通の友達も多かったから、必然と仲よくなって。とにかく価値観の合う人だった。時代背景から言うと、裏原全盛期が始まる前夜って感じで。LONDON NITE(※大貫憲章が主催する30年以上続くロックイベント)とか、音楽カルチャーに触れていたような同い年くらいの男の子達が、企業に入らずに“自分達が好きなことしかしない”みたいなことを始めている匂いがプンプンしている時代。だから私はメーカーで働いていたけど、そこを辞めて何かを始めることは必然だったと思う。あの時代にあの場所であのコミュニティで生きていた人達みんなが、それを感じていたから」

「そんなときにTAKIちゃんと出会って、とにかく可愛いお店をやりたいってなりまして。最初は、“ヘアピン屋”をやろうとしたり(笑)。そのあとTHE MAD CAPSULE MARKETSっていうデジタルハードコアバンドの、女の子用ツアーTシャツをKatieでつくったのが最初です。当時は女の子のバンドTはなくて、メンズのSサイズを着るしかなかったから。すごくタフなバンドのツアーTシャツを、当時ツインテールをしたミニスカートのいわゆるバンギャルの若い私達がつくって売るという(笑)、“タフなパンクを究極にガーリッシュな着こなしで”ってスタイル。
この図式はとても新しかったし、ある意味Katieの概念が完成されているのかも。甘くもあれば辛くもある。“ガーリー”は闇がしっかりあって、欲深くて。無垢とかで言い逃れできない。可愛いものと暴力的なエッセンスを含んで表現する、その相反する要素がどちらも味わえるKatieらしい出来事だった思います」

そんなLINDAさんのセンスや感覚を培ったものとは
「“小さいころに親が家でロックを聴いていて~”みたいなかっこいいエピソードはぜんぜんなくて(笑)。お堅いクリスチャンの学校に通っていたし。それゆえの反逆心からか、ロックスターの衣装とか、ラメやキラキラのビジュアルにやられっぱなしの子どもだったのは覚えています。学校がミッション系だったから、小学校のころは毎週日曜日に礼拝に行っていたんだけど、帰り道にレコード屋でとにかくジャケットを漁ったり。生意気ですが(笑)。ディスコメイクとか、後ろから光が当たったロンドンブーツとかにすごく惹かれて。いちばん戦慄が走ったのは意外とストーリー性のあるモータウン系やパンクカルチャー。赤い革パンのお尻の寄りのジャケットとかを見て、そういうテクスチャーに魅了されていったのは確かです。
やっぱり、音楽カルチャーから受けた影響は大きいです。いろんな音楽が好きですが、パンク、ゴスときたら流れで学生のころは私は『耽美で行く』と決めていて……。その一つに、太宰治を読むとか。そしてその先に澁澤龍彦がいて。彼が描く世界との出合いはものすごく大きかったと思う。澁澤の本を手に取ると、それに付随してジョン・ウィリー(“拘束された女性”に対するフェティシズムを表現したアーティスト)やベティ・ペイジ(ボンデージモデルの草分け的存在)、ジョルジュ・バタイユにつながっていくことになって。登場人物がみんなかっこいいし、凄みもあって。とにかく暇があれば妄想ばかりしていました(笑)。
Katieのビジュアルには足元もよく出てくるんだけど、それは可愛さの中に残虐性も秘めたガーリーの象徴だと思っていて。今でもそのあたりのカルチャーから受けているインスピレーションはすごく大きいです」

Katieの22年間
影響を受けた本やバンド、アーティストたちがKarieのシーズンテーマを生むインスピレーションになる一方で、その選び方はすごく慎重にしていると話すLINDAさん。
「時代に合っているか、今再注目するかどうかの見極めは、私達なりにすごく重要。物をつくるってやっぱりお金がかかるから。二人でアイデアを持ち寄ってテーマを決めて、言葉やビジュアルの切り口を探っていく。私はすぐややこしくしちゃうから、そこはTAKIちゃんの客観的な目で見てもらって。
さらにグラフィックに関しては甘い内容のテキストやセリフ、詩的なことを書いたりもするけど男性デザイナーの視点が最終的に入ってこそ。なんというか『ガールズパワー』がヒステリーすぎない仕上がりになっていることは男性の視点という理由もあるのかと。私もTAKIちゃんもある意味、情熱を持っての22年でしたが、二人ともやはりちゃんと商売がしたいということなんだと思います」

意のままに進みながら、冷静に世の中を見てきた二人。だからこその、Katieの22年間。
「可愛いでしょう?Katieガールズ&ボーイズ!!」
LINDAさんが見せてくれたのは、今のKatieに携わる全員が写った写真。Katie20周年パーティのものでした。
「一人じゃ絶対に無理だったし、TAKIちゃんがいたからできたこと。二人でやれなくなったら、もうやめます。一人でやっていたってかっこよくないですし、あらゆる意見や考えがあって当たり前だし。進もうかやめようかっていう温度感はすごく足並みが揃っていて。暴走することもない。妄想と無駄なことが大好きな私も、商売としてのKatieでそれはない。今のKatieは、大学生から20代、30代、40代、男性まで、各世代とジェンダーレスなKatieスタッフ達との関わり合いで成り立っていて、そこで知る生態学的な感動は尽きないです。時代が“個”に向かっている世の中だし、お一人様の食事や趣味に走ればもちろん寂しくないし人生を謳歌できるかもしれない。自立している女性は多いですし。でも、群衆の美というか、年齢の違う人達や性別を超えたチームで同じ方向を向いて表現することや達成感はやっぱり個人でやっていたら味わえないのかなと思う。
Katieは隙間産業的な少人数ではあるけれど、ある程度のファン層を巻き込んできたし、スタッフ含めKatieを好きでいてくれるお客さん同士も同じ匂いをかぎ分けて集まった人達だから、見えないところで深かったりするんだと思います。コミュニティに属していなかったら知ることができなかったことがたくさんあると思う。だから、人に興味がないとか欲がないって言わないでほしいです。何でもいいので、“WANT”があったほうが人生楽しいですし。欲深く生きるほうが後悔はないと。何があったとしても、やっぱり最終的に面白くて笑えれば、それは夢が叶っているんだと思います」

LINDA MITSUI
三井リンダ・1997年、TAKIさんと二人で東京・代官山に「Katie」を立ち上げる。それぞれの感性を原点に、自由で自立した女性が併せ持つ可愛さと強さ、甘さと辛さなど相反するものをデザインに内包しタイムレスなものをつくり続ける。
Interview_Sonoko Fujii