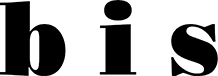Interview / 2025.05.01
【クリエイターにインタビュー】映画監督・山中瑶子のクリエイションの裏側
bisと親和性のあるさまざまな分野のクリエイターにインタビュー。今までの遍歴やクリエイションの裏側に迫る。今回はカンヌ国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を女性監督史上最年少で受賞した山中瑶子監督が登場。
Yoko Yamanaka
X:dwnwakeup
1997年生まれ、長野県出身。19歳で撮影、初監督した『あみこ』がPFFアワード2017で観客賞を受賞。国内外で評判を呼んだ最新作『ナミビアの砂漠』のブルーレイがハピネットファントム・スタジオより5月9日に発売予定。

最新作『ナミビアの砂漠』より ©2024『ナミビアの砂漠』製作委員会
どんな幼少期を過ごされていましたか?
保育園のころは、写真などを見返すと群れから外れて無表情でひとり遊びをしている子どもだったようです。わりと早くから絵を描いたり黙々と作業をするのは好きだったみたいで、絵画教室にも10年くらい通っていました。きっかけは忘れてしまいましたが、絵画教室に通う前から母と動物園に行ってキリンの絵を描いたり、雨の日には家の中で花瓶のデッサンをしたり、いろいろなところで絵を描いていた記憶があります。なので、おそらく母親がやりたかったことをやらせてもらえていたんだと思います。
小学校時代はどうでしたか?
小中と集団生活をするうちに、大人に対して不信感が募っていき、次第に反抗的な態度を取るようになっていきました。日本の教育の根幹にある「みんなで同じ方向を向きましょう」という方針に適合できなかったことが大きいです。当時小学校の担任で意識の高い先生がいたのですが、うちのクラスだけ休みの日などにボランティア活動をさせられたりしていたんです。そのころ感じた、ひとりひとりの意思や自我を尊重してもらえなかった記憶が今でも鮮明に残っていて、そこから世界に対する不信感のようなものが根底に根付いていきました。作っている映画にもそのような意識が表れていると思います。『魚座どうし』はそのころの担任の先生が嫌だった記憶を思い出して作りましたね。考えてみればほかの作品でもまともな大人が出てきたことはあまりないのでいい大人というものが描けないのかもしれない(笑)。
映画にハマったきっかけは?
高校の美術の先生がきっかけでした。高校時代は、学校に行く時間に家は出るんですけどまず映画を観て午後から学校に行き、気になる授業だけ出席したりしていて。美術の授業には必ず出ていました。その先生は社会に適合できていない、いわゆる”先生“のイメージからはかけ離れた人だったので、当時はこういう大人もいていいんだな、とかなりポジティブに捉えていたんですが、今思い返すと変なところもたくさんある人でしたね。その先生が芸術とは何かということをかなり意識的に教えてくれていたのでありがたかったです。そういう人と10代のうちに出会えたのは自分にとって大きなことでした。
大学の進路を決めた理由は?
高2のとき進路希望を書かねばならず、やりたいことは特になかったのでどうしようかと思っていたのですが、そのときちょうど映画にハマっていたので映画を学べる学校を調べて志望校にしたんです。そこから模試のたびに志望校を書き続けているうちに気持ちが固まっていきました。はじめから特段に映画監督を目指していたわけではなく、子どものころから毎日同じ時間に起きて仕事に行くのは難しいだろうなと思っていたので実は会社勤め以外ならなんでもよかったんです。
日本大学芸術学部に入学されましたが、入学後すぐに映画を撮り始めたのでしょうか。
受験期間中に映画監督という仕事は曖昧な職業だし、女性のロールモデルになるような人もそもそも人数が少なかったので、一体どうしたら映画監督になれるんだろう……と真面目に考えていました。そのとき「撮影所システムもない今、助監督になっても仕方がないし、映画監督になるにはPFF(ぴあフィルムフェスティバル)に入ることが必要だ!」と思ったんです。だから大学生になったら映画を作ってPFFに応募するぞ、と意気込んで入学したものの、いざ大学に行ってみると授業の進捗が遅くて、卒業制作でも30分尺の映画しか作れないという制約があったんです。当時はこのままだとPFFに辿り着く前にやる気が失われてしまうという焦りがありました。その結果、大学にもすぐに行けなくなってしまい、その後は映画をひたすらにいっぱい観て2年生に上がる際に大学を休学しました。相変わらず映画をたくさん観続けているうちに、このまま映画だけ観ていると、自分が理想としているものと、自分ができることのギャップがどんどん開いていって映画が撮れなくなってしまうのではないかと思い、直近のPFFに出そうと思って作ったのが『あみこ』ですね。3月が締切りだったので9月ごろから考え始めました。

初監督作品『あみこ』より
『あみこ』は主人公も高校生ですし、ご自身の体験を基にしていたのかと思っていました。
当初、エドワード・ヤンみたいな映画を作りたいと思っていたのですが、19歳には描けることも限られていたので、知らない範囲のこと、想像でしかないことよりも、知っていることのなかから物語を描いたほうがいいのかなと思っていました。当時シナリオの先生だった古厩智之監督の「半径5メートル以内から始めなさい」という教えにも影響を受けました。私は自分の半径5メートル以内で映画を作るとむしろ稚拙だったり、独りよがりになったりするのではないかなと思っていたんですが、むしろそういうパッションを感じられたほうがいいということだったんでしょうね。
でも『あみこ』はそのパッションだけでなく、映画愛にも溢れた作品ですよね。
そうですね。たった1年間で得た知識を躊躇なく使えるところはすごいですよね。明らかなオマージュなんて、今だったらできるかわからないですね。無知だからこその強さというか。
何か参考にした作品はありますか?
先ほど言ったエドワード・ヤンは当時夢中になってはいたのですが、これは真似できないなとすぐに気がついたのでオマージュや参照はしていません。たくさん映画を観ているときに、いいシーンだなとかいい撮り方だなと思ったことはメモしていて、それをそのまま取り入れたりしていましたね。精神性でいうと、イエジー・スコリモフスキの『早春』や、テリー・ツワイゴフの『ゴーストワールド』の影響は強いかもしれません。
映画の技法は観た映画から学んでいったんですね。
マスターショットについての分厚い本などをいろいろ買って読みましたが、ハリウッド映画を参照したりしていて、学生の自主映画では再現できないことも多くあまり参考にならなくて。”一から自主映画を作ろう!“というような簡単なハウツー本みたいなもののほうが役に立ちましたね。
PFFに向けて準備を進めていったわけですね。
そうですね。過去のPFF入選作品で観ることができる作品は全部観たり。こういう作品が好まれるんだな、ということを分析したりしていました。だから『あみこ』は意外と、傾向と対策じゃないですけれど、いろいろ作戦を練って作っていて、ただやりたいことだけをやっていたわけではないんですよね。
『あみこ』はPFFで入選、観客賞を受賞し、さらに世界各国の映画祭にも行かれたと思いますが、その当時を振り返るといかがですか。
1年間、月1くらいのペースで各国の映画祭を回っていたのですが、遊びにいっているわけでもないし、映画祭での自分の立ち位置もわからず大変でした。さらに日本に帰ってきたときの生活もめちゃくちゃで、ストレスが結構大きく……。でもそのときの経験があったおかげで、今回『ナミビアの砂漠』であちこち行っていますが、それぞれなんのために行くのかがやっと理解できるようになってきましたね。
そのころ映像のお仕事は何か並行してやっていたのでしょうか。
ちょうど2月のベルリン国際映画祭に参加しているときに『21世紀の女の子』の脚本を出さなければならないタイミングだったのを覚えています。5月にはまた別の映画祭と映画祭の間で、『21世紀の女の子』の撮影をしていました。
『21世紀の女の子』が公開された当時は若い女性監督の方々が一気に紹介されていくタイミングでもありましたね。
15名の監督が参加したオムニバスでしたが、今思うとああやって人数を可視化することはとても重要なことだったんだなと思いますね。(企画、プロデュースを担当した)山戸結希監督は当時、今の私と同い年くらいだったと思うのですが、よくやったな、と驚きますし、こういうことを考えていたのかな、と当時の山戸監督が見ていた景色を身をもってわかってくるようになってきましたね。
『21世紀の女の子』のあとは、どんな作品を撮っていましたか?
文化庁のプロジェクトに応募して35㎜フィルムの短編『魚座どうし』を作りました。また三浦透子さん、古川琴音さん主演で『おやすみ、また向こう岸で』という単発オリジナルドラマも並行して作っていました。コロナ前で5年以上前のことになります。そのころからいくつか長編の企画はあったんですが、どれも途中で降りたり、モチベーションが保てなくなったりしていたところでちょうどコロナ禍に入りました。一度休みたかったというか、自分が何をやりたいのかが結局わからなかったので、リフレッシュしようと思いました。その後すぐ京都に移住しました。京都は東京と違って流れる時間がゆっくりで、そこに最初は救われていたのですが、2年目くらいからは時間がたくさんありすぎて物事を考えすぎてしまったのか、だんだんと精神的に不調になってしまって。企画はたくさんあるのにもう現場に戻れないかもと思い始め、このままではいかんと思って2年前に東京に戻ってきました。そのとき、それまでずっと長く伸ばしっぱなしだった髪の毛を切ったのですが、そこからすべてがうまくいき始めたんです。また、インドにも行っていたんですが、帰ってきてから『ナミビアの砂漠』を一気に書き上げました。精神的に参っていたところから抜け出せた感がありましたね。鬱だったときに書いていたものは結構支離滅裂だったりしたので、抜けられた人間が書いたものになってよかったです。

35㎜フィルムで撮影された短編『魚座どうし』より
今もほかの作品をいろいろと準備されているのでしょうか。
まったりですけどあります。まったりにしておかないとモチベーションを保てないので。根を詰めて取り組むのは半年くらいがちょうどいいんですよね。『ナミビアの砂漠』は2023年の5月に企画が動いて、12月末に完成して、その5カ月後にはカンヌにいました。
ご自身の作品を通してのテーマはありますか。
完成してほかの人が見たときに見えてくるものがあるかもしれませんが、普段テーマから映画を作るわけではないので自分ではわからないですね。こういう感情とか、こういう情景が見たいという細部からしか書けないので、大きなテーマは設けてないです。
作品作りのきっかけはどういうところにあるんでしょうか。
どうしたら映画になるかの糸口は手を動かしているうちに見えてくるというか、とりあえず書いてみて、そこから見えてくるものを手掛かりにして立ち上がってくることが多いです。なので、散歩をしているときにふと閃いたり……ということはまずないです。
映画監督を目指すきっかけになった映画や音楽はありますか。
音楽でいうと、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、レディオヘッド、ニルヴァーナは中学生のときの三大巨頭ですね。この3つのバンドは自分にとって、ものを作りたい人の初期衝動そのままのようなイメージで。中学生のころはまだ映画にはハマっていなかったので、音楽を聴くことによって、何かを表現したいという創作への想いを募らせていました。マイブラは今でも聴くと初めて聴いたときの衝撃を思い出すことができるのですごいなと思います。
ご自身が監督を目指したときにはロールモデルとなる女性監督はあまりいなかったとおっしゃっていましたが、今は女性監督としての使命感や目指すことは何かありますか?
以前、山戸監督と大林宣彦監督のトークイベントに行ったのですがそのとき大林監督が「映画はまだ50%しか撮られていない。それは男性達が作ってきた作品です。残りの50%はあなた達が作っていってください」というようなことをおっしゃっていて、そこまで言い切ってくれる人は当時ほとんどいなかったので大きな勇気をもらいました。映画を作る人間としては、傑作なんてものはもう映画史においてはすでにたくさん生まれているからそう簡単に作れないんだ、と言う人も多いと思うんですが、そんななかで、大林監督のその発言には感銘を受けました。今後はさまざまな属性の人が監督をするだけでまだ誰も観たことのない映画がどんどん作られていくんだろうなと思います。女性監督として、とは日ごろそこまで意識していないんですけど、がんばらなくてもすでに新たな50%の一部なんだと思うとむしろ気が楽ですね。もちろんもっと女性が業界内にのびのび身が置ける環境を作ったり、ということはもはや当たり前なので、むしろ意識的にのびのびとやらないといけないなと思います。
これから映画を作りたい女性にとっても心強い言葉ですね。
そうですね。使命感はあえて持とうとしなくても好き勝手やっていきたいし、ほかの人達もそうできるようになってるといいなと思います。私は元々素行が悪いので(笑)、周りの人達からもこいつはのびのびやらせるしかない、と思われてるからかもしれませんが、「女性監督として大変なことはないですか?」と質問されると、意外と答えに困ってしまうんですよね。なので私はこれからもいい意味で素行不良を目指していきたいなと思います(笑)。

最新作『ナミビアの砂漠』より ©2024『ナミビアの砂漠』製作委員会
Text_Michiru Tobita Edit_Megumi Shimbo