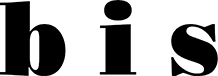Diet / 2023.04.21
牛乳を飲んでやせるって本当? 牛乳ダイエットのスゴイ効果5選
牛乳はカロリーが高く、やせにくいといったイメージをもっている人も多いのではないでしょうか。
とはいえ、牛乳にはたんぱく質やビタミン・ミネラルが豊富に含まれているため、飲み方やタイミングを工夫すればダイエット効果が期待できます。
牛乳はスーパーに行けばいつでも手に入るので、気軽に始められるのもうれしいポイント。そこで今回は、牛乳を飲んでやせる理由と牛乳ダイエットの効果を5つご紹介します。

photo:@kemidoll_oo
牛乳ダイエットって何?
牛乳ダイエットとは、毎日牛乳を飲むことでやせる効果が期待できるダイエット法です。代謝アップや脂肪の蓄積防止、ストレス軽減などが見込めて、スリムな体型を目指せます。
牛乳をコップに注いで飲むだけなので、面倒な調理も必要ありません。年間通して購入できるので気軽に続けられます。
美ボディが目指せる! 牛乳ダイエットのスゴイ効果5選
牛乳はカロリーが高くて太るイメージがありますが、栄養豊富でダイエットにおすすめの食材です。全体量を調整して、摂取エネルギー<消費エネルギーであれば太ることはないので安心してください。まずは、牛乳を飲んでやせる理由を見ていきましょう。
代謝が上がってやせやすくなる
牛乳には、筋肉やホルモンの材料などになる「たんぱく質」が豊富に含まれています。筋肉が増えると基礎代謝が上がり、エネルギーを消費しやすくなるため脂肪燃焼効果が期待できます。
また、体内で作られない必須アミノ酸も効率よく摂取できるのがポイントです。特にバリン・ロイシン・イソロイシンやアルギニンには、エネルギー消費をサポートする働きがあるのでダイエットにおすすめです。
脂肪を溜め込みにくくなる
牛乳に含まれるカルシウムには、骨を強くする働きのほかに、脂肪を溜め込みにくくする作用があります。
カルシウムが十分摂れているときは、脂肪の分解もスムーズで太りにくいといわれています。カルシウムは意識して摂らないと不足しやすい栄養素なので、手軽に摂れる牛乳を食生活にプラスして必要量を補いましょう。
腸内環境を整える
牛乳にはガラクトオリゴ糖が含まれていて、整腸作用が期待できます。オリゴ糖は善玉菌のエサになる栄養素で、腸内環境を良好に保つ働きがあります。
腸内環境が整うとお通じもスッキリしやすくなるでしょう。老廃物の排出もスムーズになり、やせやすくなります。
満腹感を得やすく食べ過ぎ防止につながる
ダイエット中は空腹感が辛いときもありますよね。そんなときは、牛乳を飲んで空腹感を和らげてみませんか。牛乳は消化に時間がかかるため、血糖値の上昇が緩やかになります。
しかし、空腹に一気飲みをすると、血糖値が急激に上がってしまうため気をつけなければなりません。血糖値が急上昇するとインスリンの分泌が増加し、余った糖を脂肪として体内に溜め込みやすくなってしまいます。結果として太りやすくなるため、ダイエット中は食欲をコントロールすることが大切です。
牛乳は水やお茶よりも腹持ちがよいので、無理なくダイエットを続けられるでしょう。小腹が空いたときに飲むと満足感が得られて、次の食事で食べ過ぎずに済むはずです。
ダイエット中のストレス対策になる
ダイエット中は食事制限や慣れない運動など、何かとストレスは溜まるもの。ストレスとうまく付き合いながらダイエットに取り組むことで成果が出やすくなります。
牛乳にはカルシウムが豊富に含まれていて、神経の興奮を抑える働きがあります。さらに、トリプトファンもたっぷり含まれているのもポイント。
トリプトファンはセロトニンやメラトニンをつくる原料であり、ストレスの軽減につながる栄養素です。睡眠の質も高められるので、お肌にとってもうれしい効果が期待できます。
【やせたい人必見】牛乳のおすすめの飲み方
牛乳ダイエットは、目安量を守って続けることが大切です。飲み方のポイントと合わせて解説します。
牛乳の目安量は1日1杯まで
牛乳の目安量は1日1杯(200ml)までです。飲み過ぎるとカロリーや脂肪を摂りすぎてしまうおそれがあるため気をつけましょう。
カロリーや脂質が気になる方は、低脂肪乳がおすすめです。普通の牛乳200mlのエネルギー量は約122kcal、脂質7.6gに対し、低脂肪乳は200mlあたり約107kcal、脂質3.8gであり、カロリーを抑えたい人に有効です。
とはいえ、普段飲み慣れている牛乳から低脂肪乳に変えると、味わいがもの足りなく感じてしまう人もいるでしょう。飲み過ぎないように適量を守れば、普通の牛乳でも問題ありません。好みの牛乳を選んで長く続けたほうが効果が現れやすいです。
牛乳を飲むときは温めてから
冷たい牛乳を飲むと内臓の冷えにつながり、血流が悪くなることで太りやすくなります。そのため、牛乳を温めてから飲むのがおすすめです。温めることで血の巡りがよくなり、代謝アップが期待できます。
冷たい牛乳しかないときは、口の中で温めるようにして飲みましょう。
牛乳を飲むタイミングも重要! 目的別のポイント

photo:@girlshino
牛乳は、飲むタイミングで得たい効果が異なります。ここからは、おすすめのタイミングを解説します。
食事前に飲んで食べ過ぎを防ごう
食前に牛乳を飲むと、血糖値の上昇を防ぐ働きが期待できます。空腹感も抑えられて食べ過ぎ防止に役立ちます。
食べ過ぎなどにより血糖値が急上昇すると、インスリンが過剰に分泌されてしまうため注意が必要です。糖の処理が追いつかなくなると余った糖が脂肪として蓄積されてしまうため、血糖値の上昇を緩やかにするよう心がけましょう。
運動前に飲んで栄養補給しよう
運動前に牛乳を飲むと、気軽に栄養補給できます。牛乳と合わせて、エネルギー源になるバナナなどの糖質を一緒に摂るのもおすすめです。牛乳が苦手な人は、飲むヨーグルトやフルーツ入りのヨーグルトなどに変えてもよいでしょう。
牛乳を飲むときは、運動する30分前に飲みましょう。ただし、牛乳を飲んで胃が重くなる人は、運動の2時間前に摂取するなど、消化時間を考えて時間を調整してみてください。
運動後に飲んで筋肉の成長をサポートしよう
代謝アップを期待したいときは運動後30分以内に摂取するのがおすすめです。たんぱく質が豊富な牛乳をこのタイミングに飲めば、筋肉を効率よく増やせます。
寝る前に飲んで就寝中に筋肉の回復を目指そう
夜に牛乳を飲むと、筋肉の修復に効果的です。良質な睡眠を心がけると、筋肉の修復をサポートする成長ホルモンが分泌しやすくなります。また、牛乳には脂肪を溜め込みにくくする働きもあるため、活動量が少ない夜に飲むのがおすすめです。
さらに、牛乳に含まれるトリプトファンは、セロトニンやメラトニンの原料になる栄養素なので、安眠効果も見込めます。セロトニンには精神を安定に導く働きがあるため、リラックス効果も期待できて良質な睡眠につながります。
小腹が空いたときにおやつ代わりにしよう
おやつを牛乳にすることで、甘い物を食べるよりも摂取エネルギーを抑えることができます。
例えば、どら焼き1個172kcal、カステラ1切れ160kcalです。牛乳1杯(200ml)は、122kcalなので、摂取エネルギーを控えたいときは牛乳を選んで効率よくダイエットをしましょう。
ただし、飲み過ぎると太りやすくなるため注意が必要です。目安はコップ1杯(200ml)までなので、適量を守りましょう。
牛乳ダイエットを行うときの注意点
「牛乳ダイエットを行っていて調子が優れない」「なかなかやせない」など、思うように効果が出ない人もいます。牛乳ダイエットを成功させるために注意点も把握しておきましょう。
牛乳が合わなければ無理せず代替品を選ぶ
牛乳を飲むと下痢になってしまう人もいます。これは牛乳に含まれる乳糖を分解できない「乳糖不耐症」が原因かもしれません。
牛乳が苦手な人は無理をせず、代わりに豆乳を選んでみてはいかがでしょうか。豆乳にはたんぱく質や食物繊維が豊富に含まれているので、ダイエットにもおすすめです。
牛乳を飲むときは適量を守る
早くやせたいと思っても、飲み過ぎは逆効果です。胃腸に負担がかかりやすく、下痢や便秘の原因にもなりかねません。1日1杯(200ml)を守って継続することで、やせやすい体質が目指せます。
バランスのよい食事を心がける
牛乳を飲むだけでやせるわけではありません。やせるためには、栄養バランスのよい食事を心がけ、その中に牛乳をプラスする意識でいることが大切です。
1カ月以上継続する
牛乳ダイエットは即効性がないため、継続することが重要です。最低1カ月続けることで少しずつ変化が見られるようになるでしょう。
運動も合わせて行う
より効果を期待したい人は、運動も合わせて行うことをおすすめします。日常生活の中に、ヨガやウォーキングなどの有酸素運動を取り入れましょう。
運動する時間がない人は、「ひと駅分多く歩く」「エレベーターではなく階段を使う」など工夫してみてください。
健康的にやせるなら牛乳がおすすめ!
牛乳には、たんぱく質やビタミン・ミネラルが豊富に含まれています。筋肉量を増やして基礎代謝を上げたり、脂肪の蓄積を防いだり、腸内環境を整える働きも期待できます。日々の食生活に取り入れやすいので、ダイエットにも最適です。
ただし、牛乳を飲み過ぎると下痢や便秘の原因につながるおそれもあるため注意が必要です。牛乳ダイエットを行うときは、目安量の1日1杯(200ml)を守りましょう。体調に合わせて無理をせず継続してみてくださいね。
この記事を書いたのは……管理栄養士 下田由美さん

管理栄養士。約10年間、病院・施設・保育園で幅広い年代の「食と健康」に携わってきた。その中で「食」と「心」は密接に関係していると気づく。現在は、「食はココロとカラダを元気にする」をモットーに管理栄養士ライターとして活動中。健康や栄養に関する記事執筆や監修、レシピ作りなどを行っている。